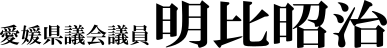国の再生を願う。(2011/2/1)
良識の府(国会)が正常化し、社会の閉塞感と崩壊を食い止め、再生させなければ、この国は大変なことになる。
ことの他寒い年明けの毎日が続いていますが、如何お過ごしでしょうか?
相変わらず景況も改善の様子も見えず、梅の便りも聞きながらもうきうきする気分にはなれません。
先月末から通常国会が始まりましたが、日本の総理大臣の所信表明演説と、アメリカ大統領も年初に一般教書を発表していますが、その姿を対比してみると、全く日本の総理は大きな声で意気込んではいるものの聞く人の心に響かない、国会そのものがそんな雰囲気で野次まで飛ぶ始末、片やアメリカでは全員が総立ちで、与党も野党も無い共鳴する発言にはみんな拍手で協賛の意思表示をして、一人ひとりに責任感が溢れる雰囲気で演説が扱われている。これが責任と良識ある国会のあり方だろう。
アメリカでこのほど発表された国債の格付けで、日本はこの政権の姿勢も含めての評価で、1ランク落とした。これに対する総理のコメントで「わたしは、それにはうといから」と記者に答えているが、こんな経済も財政もわからない無責任が本質の人が、この国の総理大臣だから格下げは当然だろう、だが困るのは国民だ。国民の預貯金を召し上げられても国の借金が片付かない日が、近かじか(2013年で1000兆円のバランスが崩れる)来るといわれている。
課題はみんなわかっているのだ、苦労も困難も分かち合って、力を携えあって皆で今頑張らなければならない。本当の人間力を取り戻し、この国を再生しなければならない。
気づいた人は勇気を持って、躊躇せず1人でも鐘や太鼓を打ち鳴らし、この閉塞感からの脱皮を図る活力を呼び起こす努力をしよう。
私も頑張る。
引き続きのご支援と、ご指導ご鞭撻をどうかよろしくお願いします。
私もこの混乱から逃げずに、むしろ向ってゆく使命感に燃えてきた。
まず一隅を照らす運動だ。
感性が理性を超克する瞬間
=ICU(集中治療室)から消えた男の物語
-月刊誌「致知」の《巻頭の言葉》より抜粋引用=アサヒビール名誉顧問 中條 高徳
『八十三歳、決然たる覚悟で』
人生の終末に来て極めて得がたい体験をしたので、親愛なる『致知』の読者に率直に伝えたい。
筆者の早朝の行ともいうべき靖国詣は、四十数年に及ぶ。筆者の現在の最も重い役割は、国家のために身を捧げ、その靖国神社に眠る二百四十数万柱の「英霊にこたえる会」
の会長職である。10月に山陰ブロック、引き続き九州ブロックの総会と強行軍が続いたゆえなのか、早朝の九段の坂を登る時、呼吸の苦しさを感じ始めていた。
だが、慣習の大声の発声、つまり深呼吸を三回重ねると胸の苦しさは消えていた。そして競歩、逆立ち、ラジオ体操、腕立て伏せ五十回といつものメニューをこなしていた。
翌日10月30日の富山の講演が気がかりだったので、主治医の門を叩いた。お世話になっている阿部先生は心臓の権威だ。診断するや「これは心筋梗塞。動いてはならぬ」との冷たい宣言。
急な事態に不安がる家内と救急車に乗り込む。事態はどんどん思わぬ方向に展開してゆく。救急車の中で筆者の頭の中をよぎるものは、明日の講演のことのみであった。
この講演は尋常なものではなかった。
富山、石川両県下のロータリアンの地区大会が前年に決定された。ホストクラブは新湊クラブ。その基調講演の講師選定がA氏に命ぜられた。
拙著『おじいちゃん戦争のことを教えて』(致知出版社)を読んだA氏は、彼の表現を借りると、目から鱗が落ち、いかに日本の歴史に疎く、戦争の真実を知らなかったかということに気づき、他の拙著を4冊も読んだ上で、この大会の基調講演の講師は絶対中條氏だと決めた重い経緯があった。
秘書から‘中條倒る’の第一報を受け取ったときのA氏の周章狼狽ぶりが目に浮かぶようだった。直ちに致知出版社の藤尾社長に連絡を取り、代役として渡部昇一氏、田母神俊雄前航空幕寮長にお引き受けいただくよう調整をお願いした。しかし急なことであり、あいにくお二人とも予定が入っていた。
その瞬間、「乃公出ずんば解決の途なし」と別段力むこともなく、83歳の老人は富山行きを決然と覚悟した。だがそれからが大変であった。
現代医学の良識は、このような暴拳ともいえる非常識な行動を許すはずがない。
数人の先生たちの熱っぽい説得が枕辺で続いた。当然のように女房、子供たちの血の搾るような説得も続く。
ベッドの中から筆者は「老人だが、現代医学を無視するほど粗野では決して有りませぬ。しかし80数年も生きてくると説明しきれないエトバス(何か)あるいはパッション(情熱)と言っていいのかもしれませんが、そうゆうものが湧き上がり、身体中がもえたぎるのです。先生方がいかに医学の理をお説きになろうとも、この老人の考えは絶対に変わりませぬ。お許し無ければ、裸足でも出ます」と、合掌しながら説得する事一時間あまり。ついに先生達は条件付ながら外出を許してくれたのだ。筆者は、これぞ芳村思風、行徳哲男両先生らが説く感性が、日本医学の最高峰とも言うべき「医学の理」を超克した瞬間と見る。
『溢れ出た涙。』
先生たちの出された条件は次のようなものであった。
1・付添い人を必ずつけること
2・全行程車椅子で移動する事
3・水を絶対飲まぬ事
4・講演は座ってやること
5・可及的速やかに本院に戻る事
更に先生達は、この強情な爺のために、直ちに講演会場に近い富山中央病院にコンタクトをとられ、筆者のカルテを付き添う委任に託されたのだ。その友情溢れるありがたい行為に、筆者はベッドの中でただ合掌するのみだった。
付添い人に選ばれた息子とともに、朝一番の便で富山に飛び立った。飛行機の中で、息子に気づかれないよう、私は手帳に遺書を書き記した。「我、事において後悔せず。だが皆さんに迷惑をかけた。許し給え。和歌子(妻)よ、後を頼む」空港に出迎えたA氏は、筆者を目の前にして喜色満面。感極まって声にならない。先生たちの約束はしかと守った。だが座ってはじめた講演は、七、八分したら立ち上がっていた。付き添いの役割を担う血を分けた息子ですら演題に近づき得なかった。これも感性のもたらすものなのだ。最終便で戻った深夜の空港に、藤尾社長と、致知出版社専務・柳沢女史の出迎えのお姿を見出した時は、胸が詰まって老いの涙を抑え得なかった。
ただ一直線に病院にひた走る。当直の先生、ナースの皆さんが拍手で出迎えてくださった。このような愛情に包まれ、11月9日、天下の名手に5時間をかけて施して頂いた心臓の修復工事は無事成功。文字通りの生還を果たした。ツギハギだらけの我が心臓だが、これからも『致知』の読者とともに人間学の研鑽に精進する事を誓う。