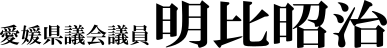何時まで続く下り坂(2012/7/1)
世界の動きに目を向けておこう。
アラブに春を!と、長期独裁政権打倒に荒れた中東であったが、未だ民主政権の確立には至っていない。民族や宗教が絡み、中々思うようには行かないものだ。
またギリシャの財政破綻に端を発しているヨーロッパ諸国連合(いわゆるEU)の結束も、ドイツを中心に連携の維持を図っているのだが、スペインの金融危機など、諸国の財政状況は悪く、共倒れ回避のためには脱退も論じられ、基盤が大きく揺らいでおり、経済不況が深刻化している。
またアメリカは、未だにリーマンショック後も不況が続き、株価の低迷も続いている。このように先進世界全体が経済不況に喘いでおり、ここへ輸出で著しく発展してきた新興諸国、特に世界の工場として発展著しかった、中国は輸出にブレーキがかかり、成長がストップあるいは鈍化してきており、ここへ部品や資金を投入してきた日本の産業も、成長が見込めない状況だ。
デフレが続き円高が続くが、これらの対策は世界に目を投じていないと、どうにも解決できない問題だ。
国内的にエネルギーの問題もあるが、世界経済に目を配り、日本産業や企業の振興をはかり、雇用の確保をしなければならない。
一体この国は何処へ誰が導くのだろうか?
国会も延長し、「税と社会保障の一体改革を」と、野田政権の意気込みに、中身の見えない改革案と増税案がこのほど国会で議決された。
自民党・公明党も最終的には修正協議に応じ、多数で議決されたのではあるが、肝心の法案の提出者である、政府並びに政権与党の民主党の議員が、多数反対行動をとった。こんな節度もルールもない政党に、国の舵取りを委ねていてこの国はどうなるのだろう?国民が選んだ人達がとる行動なので、国民に責任が返ってくるのだろう。このことは肝に命じなければならない。
だが、国民が託した政党のマニュフェストなど全く守れず、国民の信も問わずに3代も党首が交代している勝手は、国民に責任はない。党であり国会議員の責任だ。
もう信頼できる国会でなくなったのだが、誰に託せば良いのだろう。
いよいよ党の綱領もない未成熟政党である、民主党の分裂は必至だが、頼りになる政党として、自民党に支持が戻ってこないところに自民党も問題がある。
今後は選挙にらみで、一層国民そっちのけで政局争いに向かうのだろう。もう行き着くところまで行かなければ、立ち直れないのだろうか?
世界に信頼されるインテリジェンス国家を、国民みんなで目覚めて目指そうではないか!
暑さに向かいますが、お見舞い申し上げます。
さて、これから暑さも本番となりますが、原発の稼動停止により節電はやむを得ません。
暑さを凌ぐには自然に逆らわず、付き合うことが大切です。病院の電源など、命に関わることにまで電気を止めることは出来ません。
知恵と工夫で、乗り切りましょう。
自分ひとりくらいで体制に影響ないだろうと、決して思わず節電を実行しよう。
昭和の遺言状
― 一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め。 ―
月刊誌「致知」の《巻頭の言葉》より抜粋引用=アサヒビール名誉顧問 中條 高徳
『自らの国は自ら守る』
「昭和の日」を祝う集いが明治神宮で催され、国を想う人達が千人余り集まった。頼まれ筆者が「昭和」を語った。
齢八十五に達した筆者の頭の中を、『方丈記』(鴨長明作)の名文が去来した。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためなし。世中にある人と栖と、又かくのごとし。(中略)予ものの心を知れりしより、四十余りの春秋を後れる間に、世の不思議を見る事、やや度々になりぬ」
彼の倍ほどの人生を経た筆者には不思議な事がいっぱいあった。
昭和の歴史とともに生きた筆者の誕生は日露戦争からたった二十年のことであった。
特に昭和の初年は大不況で総じて貧しかったが、当時に人達は凛として生きていた。
子供たちに日露戦争の意義など分かろうはずがないが、奉天戦の3月10日は「陸軍記念日」、日本海海戦勝利の5月27日は「海軍記念日」だった。いずれの日も前線で戦った軍服を着た兵隊さんが学校にやってきて意気揚々と武勲を語った。
家では「縄なう父は過ぎしいくさの手柄を語る 居並ぶ子供はねむさ忘れて耳を傾けこぶしを握る」 を歌っていた。
長じて歴史を学び日露戦争の重要さがわかってきた。
ほぼ500年続いた白人人種の国々による植民地化の東漸の流れは、アジア諸国に達していた。華夷思想の支那ですらアヘン戦争で英国に敗れ、支配を逃れていたのはシャム(タイ)と日本だけであった。
いわば日露戦争はその最終戦であったのだ。その世界の予想を裏切って日本が勝った意義は大きい。世界はコペルニクス的転換と褒め称えた。こうした昭和の生き様を、冷血の学者は軍事主義の鼓吹などと軽々しく論ずるが、地球上の植民地化東漸の恐ろしい事実を知った我が民族が、自らの国は自ら守らなければならないと気づいた命懸けの所作だったのだ。
『一燈から万燈へ』
こうして世界の5大国に上り詰めた我が国は、五族共存の満州国を万里の長城の外側の化外の地に建国した。先進国への説明不足や米国鉄道王ハリマンの満鉄投資拒否など、若干無念さを感じはするものの、カリフォルニアやハワイを星条旗の星に加えたアメリカとさして変わりはない。
その頃アメリカは、1776年の建国という浅い歴史ながら逐次世界をリードする立場になりつつあった。その一方で人種差別が激しく、黒人問題に悩んでもいた。
彼らにとって黄色日本人が太平洋を隔てた胡散臭い存在にもなりつつあった。
大東亜戦争の起きた年、ルーズベルトが大統領であったことは日米双方に不幸であった。彼は極端な日本嫌いであった。平和模索も求められた御聖慮に応え、10月発足の東條内閣は野村・来栖二頭立ての大使態勢で話し合いを迫っていた。これに対するルーズベルトの対応は「ハル・ノート」であった。つまり一方的な対日要求を突きつけ、日本を封じ込めようというものだったのである。
いまの日本人の9割近くがこの時の東條の役割を正確に掴んでいない。
この戦いは日本の真珠湾奇襲攻撃で始まったが、昨年末のフーバー大統領の回顧録は東京裁判史観の清算のきっかけになるほど重要資料といえよう。
つまりルーズベルトの採った政策に対しては、誰が総理であろうが、あの戦争は避けられなかったのではないか。吾戦い、そして敗れた。
勝者の手で歴史は綴られるという教えどおり、彼らの手になる「太平洋戦争史」をあらゆる機会を捉えて日本国民に叩き込んだ。陸戦法規の違反までして軍事法廷を開き、7人の首を切った。捕らえたのは昭和天皇の誕生日、裁いたのは彼らのうち6人がかつて学んだ陸士の講堂。首を絞めたのは今上陸下の誕生日とういう残酷さであった。日本のすべての否定であり、再びアメリカに抵抗することのない日本づくりであった。約5世紀間におよんだ植民地化から唯一堂々と生き抜いた我が民族の美質をすべて消すことが占領のかだいであった。個の尊厳を強く主張し、公を忘れ、権利の主張専らにして義務を疎かにするなど、我が民族が営々として築いてきた美質は音を立てて崩れていった。
経済大国にもなり豊かさを身につけたがゆえに、我われはこの崩れを容易に自覚する事が出来なかった。
佐藤一斎は解いた。
「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め」
暗夜のような戦後の日本が半世紀以上も続いてきた。
嘆いているだけではまったく解決にならない。
志ある人たちよ、一燈を提げて進もう。
やがて万燈になってこの国を照らしてくれる日が必ずやってくるはずである。