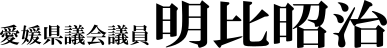卒業シーズン!(2025.3.1)

温故知新!
年度末、卒業シーズンとなるがこの1年の成果の進歩を確かめてみよう!
学生は学業や友人との出会いと発展・クラブ活動での成果を!社会人は会社や所属団体での活動の成果を!
反省のないところに進歩なしと言われる。皆で話し合ってみましょう。
特にSNSの利用による社会の発展と混乱状況は、平穏を蝕んでいないだろうか?
最近の選挙の取り組みに、SNSは必須のツールとして活用されています。スピード感を備えた情報伝達手段は、選挙の有りようも大きく変えたように思えます。
これまではコツコツと手間暇かけながら、住民と生の声や姿の見える対話や活動の様子を共有しながら選挙運動に取り組み、候補になる人応援する人が一体感をもって取り組む姿が通常でありました。最近は映像や写真で短く瞬時に情報を流し受ける事が当たり前のスピード感で取り組まれ、立候補もしやすくなったのか、これまでは候補者発掘に苦労もあった時代から一変し、多くの立候補者となりました。
しかし一方では投票率が50%を切る状況となりました。最も身近な地域密着の問題に取り組み話題としては「ああだこうだと」よく井戸端会議に加わるのだが、肝心な社会制度には問題としない、社会風潮と現象に私は非常に危機感と無常感を覚えます。
先月も書きましたが、もう一度主張します。根も葉もない偽情報をSNSで安易にとか、意図的に流し、社会を(人心を)不安に貶め、混乱させている事件(事案)が、後を絶たない状況です。事の真偽を見極める判断力を持たなければなりませんが、そんな賢人はいません。公の秩序良俗を守る法の整備と監視は、政治の責任です。早く規制の手立てに取り組まなければなりません。
この悪例は選挙の手段としても横行しています。正常善良な判断力の機能する政府(行政府)を作らなければなりません。目の前のまやかしパフォーマンスで民衆を惑わすことのない、しっかりした理念と責任感を持った政治活動と、政治家を身近なところから守り育てましょう。
県議会でも新年度に向け政策立案や予算組について、大きな課題とテーマとして
1)人口減少対策 2)DX・官民共創の推進 3)防災・減災対策 4)地域経済の活性化
を政策推進の柱として、
「人をひきつけ住み続けたい愛媛づくり」
「誰もが健康で豊かな生活を送る事が出来る愛媛づくり」
「子どもたちのたくましい成長を支える教育立県えひめの実現」
「地域の稼ぐ力と県民所得の向上」
「交流人口の拡大による国内外からの活力の取り込み」
「誰もが安心して暮らせる社会づくり」
「地域の都市機能の維持・適正化」
「リスクから県民の命を守る安全・安心な生活基盤の充実」
「環境を守り自然と共生する社会の実現」
のための具体的推進施策を、『ビルドアンドスクラップ』の姿勢で個々の事業に点検を怠らないように、チーム愛媛で取り組むことを審議と協議を深めています。
草花の香・頬を伝う風の温もり・声を掛け合う溢れる人情を大切に!
深まるほどに
足りない自分に気づく
月刊『致知」2025.3月号【巻頭の言葉】より引用
愛知専門尼僧堂堂頭 青山俊董

~ 修行に 卒行はない ~
三月、卒業生への餞に私は語る。「シュギョウに修業と修行の違いがあり、修業には一応の卒業もあるが、修行には卒行はない。むしろ深まるほどに足りない自分に気づく、というのが修行のあり方。無窮の精進を」と。
ある日、『論語』を読んでいて、子貢が孔子に語っている次の言葉に出合った。
「顔回は非常に優秀で、一を聞いて十を知る人であったが、私は一を聞いて二しかわかりません」
私は十五歳で出家したその初めに、幸い沢木興道老師に出会うことができ、ひたすら沢木老師を見つめて生きること十五年余り。三十五歳の頃出会うことができた余語翠巖老師には二十五年余り。 その他多くの師家に幸いに参じ続けることができ、私なりに一句ももらさじの思いで聞いてきたつもり。しかし残念ながら、自分の持っているその時の受け皿の大きさ、深さでしか聞けていない自分に気づいた。一を聞いて二どころか、十を聞いて一か二しかいただけていなかったということに。その一さえも貧しい自分の経験の角度からしか聞けていなかったな、ということに。
~ 生き方が鑿となって 人格を刻み続ける ~
古い話になるが、某化粧品会社から「美しき人に」というテーマでの講演を頼まれた。私は云った。「私の話は塗ったり染めたり、洗ったらはげる話ではない。どう生きるかという生き方が見えない盤となって人格を刻み続けるという話なので、化粧品会社のお役には立ちませんよ」と。それでもよいというので出かけていった。
その日の聴衆は、その化粧品会社が造っている化粧品を売っている小売店の店主を集めての講演会で、私の話の前に新しい化粧品の使い方の講習会があり、そのあとへ行って化粧品ではない”という話をした。何とも似合わない話である。話が終わった後、数人の質問があった。そのうちの何人かが「先生はどういうお手入れをしておられますか?」という質問。 “手入れではない”という話をしたのに、この人たちはやはり手入れという角度からしか聞けていないのだと気づいたことであった。ちょうどそのように、十のうちの一しか聞けず、その一さえもちゃんと聞けていない自分を自覚せねばと思ったことである。
少し違った視点から光を当ててみよう。余語翠巖老師の言葉に「真理は一つ、切り口の違いで争わぬ」というのがある。例えば、円筒形の茶筒を横に切ったら切り口は丸くなり、縦に切ったら矩形に、斜めに切ったら楕円になる。茶筒全体の姿、つまり真理は一つという姿を見ることができず、切り口しか見えていない自分にまずは気づかねばならない。
幸いに気づくことができれば、その貧し切り口を相手に押しつけることもなかろうし、一歩進めて、切り口の違いは尊重し、学びあっていこうという姿勢になるのではなかろうか。違いは積極的に学びあっていこうという例を一つあげよう。
~ すべてのものは 一つ生命に生かされている兄弟 ~
東西霊性交流の勝縁をいただき、何度か訪欧し修道院生活をさせていただいた。どの修道院も壁画は血塗られた歴史を物語るものであった。流浪の民で出発し、罪人として十字架にかけられての最期というキリスト教の歴史は、受難の歴史という一面があろう。
仏教の歴史は対照的である。 王子として生まれ、世間的な幸せは悉く満たされていた悉達多太子が、そのすべてを捨てて求道の旅に出られ、命がけの御修行の末に天地悠久の真理にめざめられた。 それを科学者の村上和雄先生はサムシング・グレートと呼んでおられる。地上に住むすべてのものが、草木も動物も人間も等しく一つ生命に生かされている兄弟、という姿勢であるから、仏教の二千五百年の歴史には血は流れていない。 話を戻そう。「井の中の蛙 大海を知らず」とは荘子の言葉であるという。大海を知らないばかりではなく、井の中の蛙でしかない自分への自覚もないことになる。井の中の蛙でしかない自分を知るためにも大海を知らねばならないのである。
九十二歳の春を迎え、ガンジー翁の語る「明日死ぬかのように生き、永遠に生きるかのように学ぶ」という言葉が響く。
”いつ死んでもよい今日只今の生き方を”の覚悟と、”永遠に生きるかのように学ぶ”の誓願のもとに、一歩でも二歩でもより深く、と願う朝夕である。