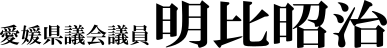米騒動?!(2025.6.1)

梅雨空にも異常?物価にも異常?
今年の梅雨入り発表は、沖縄よりも九州南部であったりして、まだらな発表に、何か先行きに線状降水帯による異常気象降雨が心配される。気温ももう真夏日が局所で観測されたりし、これまでの日本列島の様子も変わってきているように思えてならない。定説の観念を変えなければならない。
トランプさんの再出現により、世界経済の動きも激しく変わり、貿易に頼る我が国の経済にも、物価の高騰が国民生活にも大きく影響し、不安定要素がまん延しつつある。毎日の食生活の主食のコメの値段が、通常の倍以上の値段となり、米騒動も起こっている。
誰がこの不安定な波動を収められるのだろう?
トランプ関税の行方がまだ定まらない。バナナのたたき売りのように口上が激しく一体定価はどの線にあるのか、本人にも解っていないのではないかと思えるように世界が振り回され、協力同盟意識も弱体化しているように思えてならない。
一方共産主義国家体制のロシアのプーチンさん、中国の周さんは、民主主義国家群の乱れにこぼれた益をうまく掬い取って、覇権力を強めている。
以前「不確実性の時代」などと言われたこともあったが、正に今がその時代で民主主義の定義も壊れつつあるように思えてならない。世界の波動軸も芯がぶれて不安定だが、我が国の軸も不安極まりなく思えてならない。
国民の命の素である食料の「米騒動」が起こっている。食管法や農政の関係法で最も『国民の命を守る』ための「消費者」と「生産者」のどちらも国の柱として、法体制によりしっかり安定して守られなければならないのだが、そのほころびが今露呈している。メンツの問題ではない命の問題なのだ!政治も行政も誰かのメンツのために動いてはならない。守られなければならないのは国民の命であり、それをつないでゆく国民の生活である。政治を手段として口論に溺れてはならない。
参議院選挙も前にして、検めてみんなで「政治の在り方」をしっかり考えなおそう。あまりにも最近の世相はご都合の議論ばかりで進路が見えず、舵も壊れ座礁した船に乗っているような状況と思えてならない。そうしなければ、平和社会も保てず、騒動に巻き込まれ、国民の命が滅びる。
ところで米騒動の中で、愛媛県は裸麦の生産量が「日本一」で、味噌や醬油の主原料なのですが、この際栄養価の高い「麦」を米と一緒に炊き込んで食べられることを一層広めることをお勧めします。日本栄養学会では「災害備蓄の非常食用」に麦の入った食料が取り組まれ推奨されています。
因みに「日本栄養学会」の創始者は、西条市で生まれ、伊予市で育った『佐伯 矩(さいき ただす)』さんで、「営養」と言われていた言葉を「栄養」と確立されたのは、伊予市にある「栄養寺」からの活用だったようです。戦争中も「脚気」で病死した人が多かったのですが、麦ごはんでそれを救ったそうです。
また栄養学を確立するため「佐伯栄養専門学校」も創設され、栄養士の普及にも努められました。愛媛で生まれた偉人です。西条市の医師会館に顕彰レリーフもあります。明治9年生まれですから来年は生誕150年になられます。郷土の偉人を讃え、子供たちにも知ってほしいものです。
2025年5月30日東京都大田区蒲田にある学校法人「佐伯学園」に訪問、池上本門寺にある「佐伯 矩 博士顕彰碑」(長女芳子さんの墓所)にも訪ねました。
愛媛の偉人: 佐伯 矩(さいき ただす) 先生









※画像をクリックで拡大表示がご覧いただけます。
水からの学び
月刊『致知」2025.6月号【巻頭の言葉】より引用
愛知専門尼僧堂堂頭 青山俊董

~ 時と処を超えて変わらないことを真理という ~
六月のことを「水無月」と呼ぶ。若い頃、田づくりなどで一番水のほしい季節なのに、なぜ水無月などというのか、と疑問に思ったことがあった。「水の無い月」ではなく、「水の月」の意味で、「水田に注ぎ入れる月の意」(広辞苑)と知ったのは、ずいぶん後のことであった。
この水について学びたいことは山々あるが、まずは中国・中唐時代に出られた大梅法常禅師の「随流去」の一句に参じてみよう。
法常禅師は馬祖道一の会下に参じて大悟の後、大梅山中の草庵で更に坐禅辦道に精進された。頭上に八寸の鉄塔を乗せての坐禅であったという。 眠らないために。
あるとき、一人の修行僧が杖(行脚に必要な道具)の材料をとりに山へ入り、道に迷って思いがけなくも法常禅師の草庵の前へ出た。一問一答の後、〝里へ出る道を教えてくれ”というと、たった一言「随流去」と答えたという。つまり川を探し、その流れに従って行けば、おのずから里へ出ることができるというのである。
水は引力のある地球上にある限り、必ず高きから低きに向かって流れる。時の古今を超え、所の東西を超えてこのことは変わらない。二千年前であろうと、二千年後であろうと、欧米であろうと日本であろうと、変わらないことを真理と呼ぶ。梵語(インド)では「ダルマ」と云い、訳して「真理」。「漢訳して「法」となった。 文字はよくできている。「法」は「」に「去る」という文字構成。 水が流れ去る姿をもって天地悠久の真理を表そうとしたものと考えられる。
ついでのことながら「法律」という言葉仏教の言葉で、「法」が時と処を超えて変わらない真理であるのに対し、律は道徳律などと熟語して、人間同士の間の申しあわせで、時と処で変わる。永遠に変わらない法を縦糸として、織りなす横糸としての道徳律ならよいが、人間のみの勝手な考えから出たもの(たとえばオカルト宗教など)は気をつけねばならない。人間の一生にはいろいろなことがあろうが、いついかなるときも、気ままわがままな思い、人間の思いを先とせず、天地の道理、悠久の真理に随順して今ここを生きる”の教えと、まずはいただきたい。
~ いかなることにも柔軟に ~
次に学んでおきたいことは水の柔軟さである。 甲斐和里子さんの歌に、
岩もあり木の根もあれどさらさらと たださらさらと水の流るる
というのがある。渓谷を流れる川の景色詠じたものであろう。岩や木の根があり、崖があり滝つぼがある。どんな状態に出会ってもこだわりなくさらさらと。とどまるほどに力を増し、大まわりするほどに豊かになりながら、しかも前へ進むことを忘れない。
私は更に一歩進めて、岩や木の根が沢山あるほどに、崖や滝つぼのあるほどに、豊かな景色となると受けとめたい。
道元禅師は『典坐教訓』の最後の「大心」の心を「四運を一景に競う」の一句で結んでおられる。 「四運」 を 「生老病死」、つまり人間の一生といただきたい。愛する日あり、愛が憎しみに変わる日あり、成功する日あり、失敗する日あり、病む日あり、健康の日あり。 人生のすべてを生老病死の言葉で象徴され、いかなることも追ったり逃げたりせず、一歩進めて、人生を彩る豊かな景色と受けとめていこうとの教えといただきたい。
~ 小水が 岩を彫る ~
水からもう一つ学んでおきたい。釈尊は入滅されるときの遺言の言葉の中で、 「小水常に流るれば、すなわちよく石を穿つが如し」と、相続の力を水にたとえて説いておられる。 海岸などを散策していて、そそり立つ岩肌に、寄せては返す波が彫り出しみごとな彫刻を発見し、釈尊の教えをまのあたりに見る思いをしたことであった。
東井義雄先生はある時、子供にこう語りかけられた。「廊下の雑巾がけをするのに、一度に百回拭くのと、毎日丁寧に拭いて百日続けるのと、どちらが美しいか」と。丁寧に百日続けることのほうが至難である。洞山大師の「相続や大難なる」「相続は力なり」のお言葉を思うことである。
渓声は便是れ広長舌 山色豈に清浄身に非ざること無し。 夜来八万四千の偈 他日如何が人に挙似せん
中国・宋代の蘇東坡が廬山に遊び、渓水の夜流するのを聞いてつくったといわれる偈である。
天地が日夜をわかたず説きつづけてくれている言葉を、われわれの心の眼や耳をひらいて見聞せねばと切に思うのであるが。